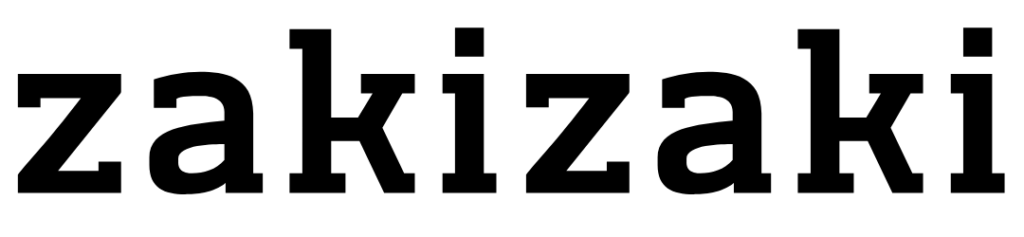『マダム・イン・ニューヨーク』とは
『マダム・イン・ニューヨーク』は2012年に公開されたインドのコメディ映画。監督を務めるガウリ・シンデー初の長編作品。
世界的に大ヒットし数々の新人賞を贈られた。
・作品情報
監督
ガウリ・シンデー
キャスト
・シャシ - シュリデヴィ
: 主人公。二児の母でインド女性。
・ローラン - メーディ・ネブー
: フランス人。英会話教室の仲間。シャシに恋心を抱く。
・ラーダ - プリヤ・アーナンド
: シャシの姪。快活な大学生。姉のミーラが婚約予定。
・サティシュ - アディル・フセイン
: シャシの夫。亭主関白。
・機内の乗客 - アミターブ・バッチャン
: 機内でシャシの隣席になったインド人男性。
・ケヴィン - ロス・ネイサン
: ミーラの婚約者。
『マダム・イン・ニューヨーク』あらすじ
・予告動画であらすじ確認
まずは映画の予告ムービーでかんたんに見てみよう。
・4ステップであらすじ確認
文字でも読みたい人向けのあらすじ。ここでは4ステップでかんたんに。
[st-step step_no="1"]・二児の母であるインド人女性シャシは良妻賢母で料理が上手。英語を話せないことがコンプレックス。[/st-step] [st-step step_no="2"]・姪の結婚式でニューヨークへ行くことに。[/st-step] [st-step step_no="3"]・言葉の壁に辛い思いをする。克服のために内緒でニューヨークの英会話教室へ。[/st-step] [st-step step_no="4"]・姪の結婚式が終わり、家族はインドへ帰る。[/st-step]
『マダム・イン・ニューヨーク』感想
ある場所に行って、成長して、帰ってくる。物語の構成はオーソドックスでシンプルだ。
それなのにこの『マダム・イン・ニューヨーク』は奥深く味わいのある作品に仕上がっている。
それはなぜなのだろうか。
ここではその謎について考察していく。
・「子ども」というスパイス
『マダム・イン・ニューヨーク』では主人公シャシの家族として二人の子どもが描かれる。
サプナ(姉・10歳くらい?)とサガル(弟・5歳くらい?)だ。
一見この子どもたちは脇役かと思いきや、実は物語の重要なテーマを担っている。
子どもは多くの母親にとってかけがえのない存在であり、宝物であり、最も愛すべき者たちだろう。
だけど、子どもというのは時として悩みの種にも、さらには苛立ちの対象にさえなり得る。
『マダム・イン・ニューヨーク』で描かれる子どもたちが担うのは後者の役割だ。
姉のサプナは英語が出来ない母親を恥ずかしく思っており、彼女のことを内心見下している。
そのことはあらゆる場面で描かれていて、母親のシャシにとって精神的な苦痛をもたらす。
一方、弟のサガルは純真で母親を悪くは思っていないが、無意識の行動で母親を困らせる。
特に、この弟のサガルは物語を動かすキーパーソンだ。
物語の後半に家族はニューヨークで再会するのだけど、夜、夫のサティシュは久々の再会に妻を求めようとする。
しかし突然部屋にサガルが入ってきて、眠れないと言い両親の間に入るのだ。
すると、久々に妻とイチャイチャしたかった夫は呆れた様子で、サガルと妻の二人に背を向ける。
これは、
- 夫婦の間を子どもが邪魔している
ということを象徴的に表している。
このように、サガルがシャシを邪魔する場面は数多くある。
たとえば、それから少し進んだ場面で、家族でニューヨークを観光中、シャシは英会話教室に行くため内緒で家族の元を離れる。
すると不運なことに、シャシがいない間にサガルが怪我をするという事件が起きるのだ。
シャシは母親としての責任を怠ったと自分を責める。
また、さらに進んだ結婚式当日の場面では、サガルのいたずらによって、式で振る舞う自慢の手作り菓子「ラドゥ」を全て地面に落としてしまう。
シャシはもう一度「ラドゥ」を作り直すことを余儀なくされ、行きたかった最後の英会話教室へは行けなくなってしまうのだ。
このようにみてみると、
- 子どもに邪魔される母親
という構図が、繰り返し強調されて浮かび上がってくることが分かるだろう。
たしかに子どもの面倒を見ることは親の義務ではあるけれど、一人の人間としての自由な時間や趣味などを我慢しなければならないのだろうか。
そういったメッセージが、サガルという子どもの役割によって、よりはっきりと伝わるようになっている。
・「伝統」というスパイス
この映画を観ると「伝統」もテーマの一つであることが分かるだろう。
インドの伝統菓子「ラドゥ」作りが上手なシャシは、常にインドの伝統衣装であるサリーを着ている。
人前で恋人同士が露骨に触れあうのを嫌い、さらに姪の結婚式はインド式で、ヒンドゥー教の司祭が執り行う。
これらの「伝統」は彼女の生活に染みついていることが分かる。
フランス人コックの恋心を頑なに拒み続けるのも、二児の母親で不貞は許されないという「伝統」の力がはたらいているのだろうと考えられる。
だが、伝統も時に足かせになるときがある。
特に最後の「ラドゥ」を落とす場面は象徴的だ。
なぜなら、「サガルにいたずらされてラドゥを作り直さなければならないから英会話教室に行けない」というのは、
- 「子ども(=サガル)と伝統(=ラドゥ)に足を引っ張られて個人的な欲望を満たせない」
というふうに読み取ることができるからだ。
こうしたことから、
- 伝統
といったことも、この映画のスパイスであることが分かる。
子どもと伝統を超えて
注意して欲しいのは、『マダム・イン・ニューヨーク』が「子どもって邪魔になるよね」「伝統ってうざったいよね」ということをメッセージにしているのではないということだ。
シャシをみてみよう。
彼女は最後の英会話へ行けなかったものの、ラドゥをしっかり作りあげ、サガルのいたずらも赦している。
そのうえで、式の終わりでは見事な英語のスピーチを披露するのだ。
これは、子どもや伝統などを何ひとつ損なうことなく、それらと上手に付き合ったうえで、自分の目標をも達成したことをあらわす感動的な場面といえる。
たしかに彼女がしたことは偉業で、誰にだって真似の出来るものではない。
だが、色々なものに縛られながらも、それらを乗り越える彼女の姿勢は世の人たちの心を動かした。
それは、「子どもや夫との関係」、「伝統やしがらみ」といった普遍的なテーマを、監督であるガウリ・シンデーが上手にまとめ上げたからこそ、多くの人の共感を呼んだのだろう。
ラドゥ作りとジャッジメンタル ~あとがきにかえて~
「judgmental(ジャッジメンタル)」という言葉がこの映画のキーワードだ。
「決めつける」という意味で、結婚式のスピーチでもシャシが使った。
この映画においては、「女は家で料理をする」だとか、「ラドゥ作りしかできない」といった決めつけに反発する意味で使われる。
『マダム・イン・ニューヨーク』は主人公が主婦で女性目線の物語だが、男性にこそ見て欲しい映画でもある。